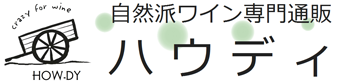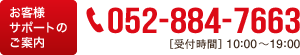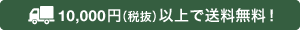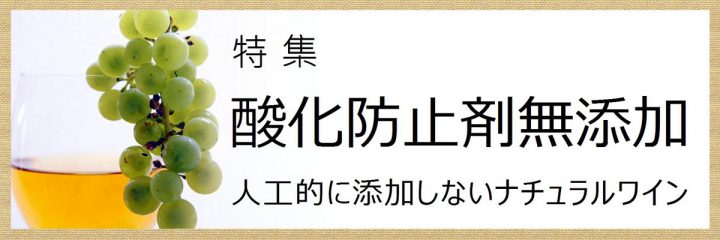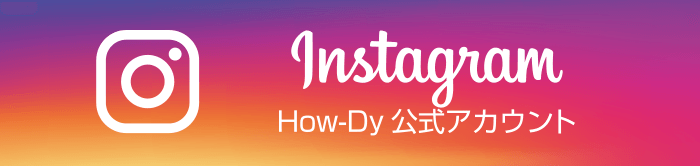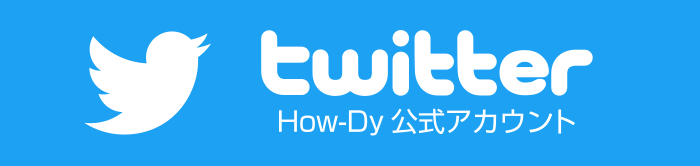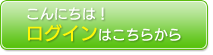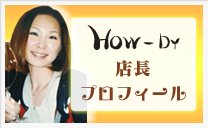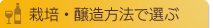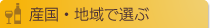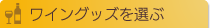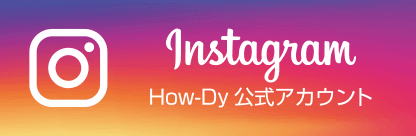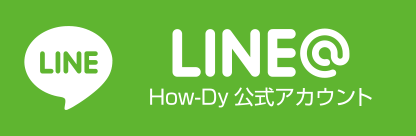酸化防止剤とはいったい何?
ナチュラルワインを知る上で、避けては通れない「酸化防止剤」の話。日を追うごとに関心が高まっているのを、現場を通して感じています。飲食にかかわる方は、今後さらにお客様への情報提供が必要となって来ることでしょう。そんな時にお役に立てばと思います。
(2022年12月更新)
目次
酸化防止剤の表示について
ワインに使用される酸化防止剤は食品添加物の1つです。2022年現在、食品添加物表示については「消費者庁」が管轄し事業者に表示方法を定めており、目的に応じた「用途名」と「物質名」を併記しなければなりません。
例えば、【原材料名 ぶどう/酸化防止剤(亜硫酸)】と表示があった場合、「/」(スラッシュ)以降が添加物の表示になり、用途名:「酸化防止剤」物質名:(亜硫酸)となります。
参考リンク
・食品添加物表示に関する情報(消費者庁)
・食品表示の内容を正しく理解するための“食品添加物表示に関するマメ知識”
酸化防止剤として使用される物質「亜硫酸」とは?
「亜硫酸」は硫黄化合物です。化学式で表すと以下のようになります。
「二酸化硫黄:SO2」+「水:H2O」→「亜硫酸:H2SO3」
ワイン業界ではよく「SO2(エスオーツー)添加/無添加」と表現する事が多いのですが、SO2を添加したワインの中には「水分H2O」がありますから、結果的に上の化学式の通り「二酸化硫黄」と「水」の化合物である亜硫酸となります。

なぜ添加するの?
ワインは通常、無菌室ではなく自然環境の中で発酵・醸造されます。空気中には、微生物(カビ、ウイルスなど)が存在しており、一部にはワインの異臭や劣化の一因となる不良なものもあります。これらが発酵・熟成途中のワインに混入し増殖すると、せっかく苦労して造ったワインが台無しになってしまいます。そうなっては、元も子もありません。このため、ワイン造りに対して不都合な微生物の増殖を抑えるために酸化防止剤を添加するのです。
また、硫黄を活用していた記録は約4千年前に遡ります。当時は素焼きの甕を逆さにして硫黄を炊き二酸化硫黄を吸着させたそうで、これが酸化防止剤の始まりと言われています。
酸化防止剤の使用量に規定は有るの?
添加物である酸化防止剤の使用量は、厚生労働省により「一日摂取許容量※」としてきちんと法律で定められています。(※生涯にわたり毎日摂取し続けても影響が出ないと考えられる一日あたりの量)
日本の果実酒に対する亜硫酸最大含有量規定は350mg/Lまでとなっています。
その規定内でワインの「醸造過程」・「瓶詰め時」にそれを入れたものは、酸化防止剤を添加したワインとなります。
また、この使用料は国によって規定が異なります。

酸化防止剤【無添加】なら、表示しなくてもいいのでは?
「無添加=人工的に入れていない」ならば、表示義務は本来無いはず。しかしながら、ここからが本格的なお話。「二酸化硫黄:SO2」はワインの酵母が自ら作りだすものでもあるのです。
ワイン酵母(サッカロミセス)は、ぶどうの糖分を食べてアルコールと二酸化炭素に分解します。しかしながら、酵母自体はアルコールが増えすぎると生きていけなくなるので、発酵過程でアルコールと他の微生物から身を守る為に、硫黄を作りだすのです。
この酵母自体が造り出した硫黄(S)が酸素(O2)と結び付き、=SO2(※1)さらに液中の水(H2O)と結び付くと、「二酸化硫黄:SO2」+「水:H2O」→「亜硫酸:H2SO3」となるのです。この量は、ごく微量で人間が感知できないほどだと言われています。
つまり、酸化防止剤無添加であるにもかかわらず、ラベルに「酸化防止剤」と書かれている場合は、このケースに当てはまるのです。

まとめ
いかがでしょうか?
今まで気にもしなかった、思っていたことと違っていたなど、いろいろなご意見があることでしょう。
消費者庁の「食品表示法等(法令及び一元化情報)」は、こちらのリンクから詳細がご覧いただけます。
ぜひ参考にしてみてください。
(※1)2021年7月7日15時まで誤表記がございました。ここにお詫びするとともに、正しい表記に変更しております事ご報告いたします。
誤:「この酵母自体が造り出した硫黄(S)が二酸化炭素(O2)と結び付き、=SO2」
正:「この酵母自体が造り出した硫黄(S)が酸素(O2)と結び付き、=SO2」
ハウディでは酸化防止剤無添加のワインを多数取り扱いしています。ぜひあなたのお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。