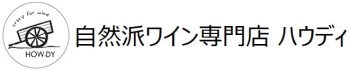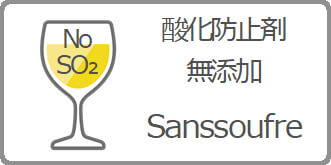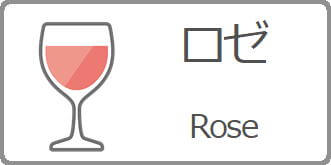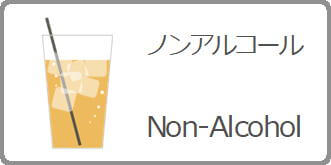350年の歴史が育む、心と体に優しい自然酒の伝統
寺田本家のお酒は、江戸時代の延宝年間(1673〜81年)に滋賀の近江から千葉・神崎へ蔵を移して以来、350年にわたり受け継がれてきた老舗の結晶です。
明治維新や世界大戦、平成から令和へと続く激動の時代を越えても「百薬の長」としての酒を造り続けてこられたのは、多くのお客様の支えがあったからこそです。長い歴史とご愛顧への感謝を胸に、現在も真摯に酒造りが行われています。
「発酵は変わり続ける」 革新と挑戦から生まれた安心の自然酒
酒造りの根幹には、23代目当主・寺田啓佐の「発酵は変わり続ける」という言葉が息づいています。1980年代には、病をきっかけに「安心して飲めるお酒」を追求し、無農薬・無添加の「五人娘」を生み出しました。
さらに「米を削るほど良い酒ができる」という常識を覆し、玄米のまま醸す発芽玄米酒『むすひ』を誕生させるなど、常に挑戦を重ねています。現在は24代目の寺田優がその理念を受け継ぎ、「味わう楽しさ」を加えることで自然酒の新たな魅力を引き出しています。
文人・歌人が愛した蔵—文化と芸術を育む精神
寺田本家は、酒造りにとどまらず文化や芸術を尊ぶ精神を受け継いできました。20代目当主・寺田憲は歌人としても活躍し、伊藤左千夫、与謝野鉄幹、斎藤茂吉といった近代文学の巨匠を支援しました。短歌雑誌の発行費や学費、生活費まで援助し、多くの書簡が交流の証として残されています。
この文化を大切にする気風は現在も息づき、多様な人々が集い交流する場として蔵を彩っています。
自然に学び、未来へ繋ぐサステナブルな酒造り
寺田本家の酒造りは「自然に学ぶこと」を指針としています。2021年からは谷津田を再生する「復田プロジェクト」を開始し、自然環境で育まれた米から奥深い自然酒を追求しています。
酒造りの道具においても、木製の甑(こしき)や竹の米揚げざるを職人に依頼するなど、自然素材による伝統的な道具を復活させてきました。千葉の山武杉を使った木桶づくりや、2020年からの100%再生可能電力への切り替えなど、環境に配慮した取り組みも進められています。
地域と共生し、笑顔あふれる未来を創造する
地域とのつながりを大切にし、2016年にはカフェ「うふふ」を開設。酒粕や麹、地元の農産物を活かした発酵料理を提供し、発酵を身近に楽しめる場を設けています。
将来のビジョンは、蔵人が酒造り唄を響かせ、「日本酒=自然酒」が当たり前となる社会を実現すること。蔵の前の通りには小さな店が並び、地域の人々と旅人が交流し、農家が誇りを持って農業に励む姿が描かれています。
創業400年を迎える2073年に向け、自然と共に発酵し続ける歩みが続けられています。
このお酒の特徴は
発芽玄米酒「むすひ」は酸味が強く、独特の香りがあり、アルコール度数が低く、従来の日本酒という概念から大変かけ離れた味わいのお酒です。
瓶の中では乳酸菌や酵母が生きていて、醗酵し続けているため冷蔵庫に保存しておいても日々風味が変わっていきます。
これは品質の劣化ではなく自然な発酵です。どうぞ安心してお召し上がりください。
また、発酵に伴い、ビン内に炭酸ガスがたまり、2~3気圧になる場合がございます。お酒がお手元に届きましたら冷蔵庫に立てて、5時間くらい落ち着かせていただくと安心です。
開栓の際には、一度に栓を開けてしまいますと中身が噴出することがございます。開け閉めをすばやく繰り返して、中の気圧を抜くように、5分~10分位かけて開栓してください。
開栓前に絶対にビンは振らないようお願いいたします。
(蔵元資料より)